米連邦公開市場委員会(FOMC)後のドル相場が下げ止まらない。米連邦準備制度理事会(FRB)は金利を引き上げたものの、パウエルFRB議長の発言に「ハト派色」がにじんだと受け止めたトレーダーによるドル売りが続き、1日のニューヨーク外国為替市場の取引終了後もドル安は続いている。ドルはどこまで下落するのか?
ドル、米ドル指数、FRB、FOMC、パウエル議長、ディスインフレ - トーキングポイント
- ドルは、FRBがよりハト派に傾いたことを嫌気した売りに押された
- パウエルFRB議長の発言は、市場では「ハト派的」と受け止められている
- 市場はFRBの見解に疑問を抱いているように見える。それがドルを沈めることになるのか?

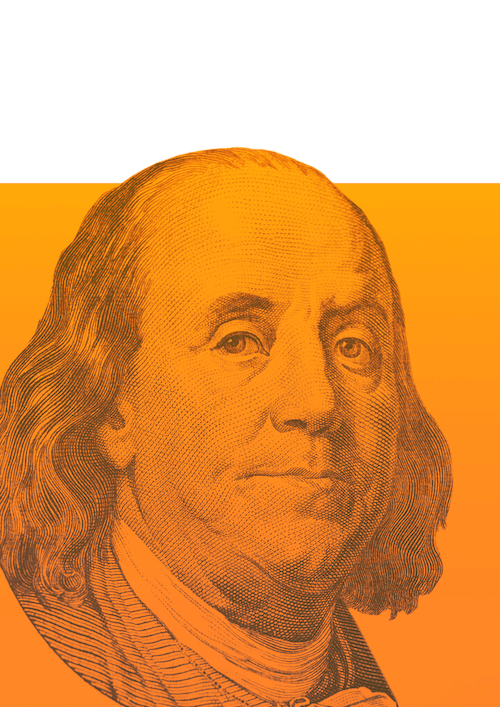
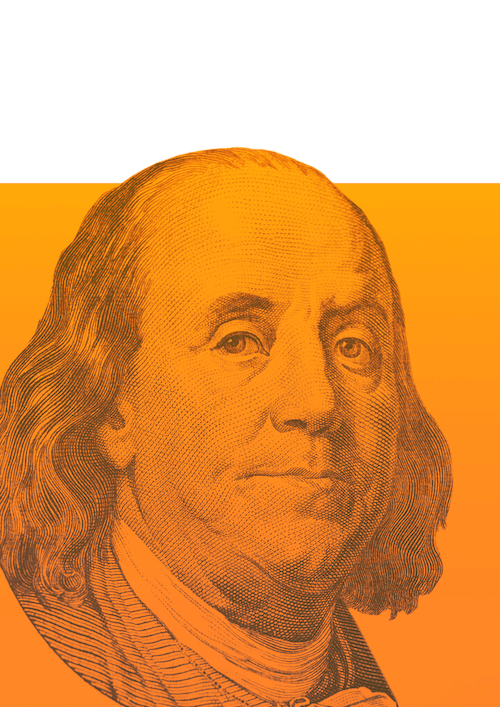
米連邦公開市場委員会(FOMC)は大方の予想通り、政策金利の誘導目標を25ベーシスポイント(bp)引き上げたが、きょう2日のドル相場は低迷している。
25 bpの利上げは明確に政策の引き締めであるが、会合後の記者会見でパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が「ディスインフレ」という言葉を用いたことで、メッセージがいささかぼやけ、市場は混乱したように見受けられる。
この発言がきっかけとなり、株式も債券も上昇したようだ。ナスダック総合株価指数は前日比2%高となり、欧州の株式相場の上昇を促した。一方、米国債利回りは、2年債およびそれよりも償還期間の長い債券の利回りが10 bp程度低下した。
長期金利の指標である10年債の利回りは3.4%を下回って取引され、昨年10月の最高水準である4.33%からは大きく後退している。
一見すると、パウエル議長の発言は合理的に見える。注目すべきは、議長が今年中の利下げ実施は考えておらず、継続的な利上げが適切と述べたことである。
また、深刻化する米国の債務上限問題に関しては、FRBが経済を守れると考えるのは禁物だと指摘し、これは議会の問題であり、FRBが取り組めることではないと明言した。
議長はディスインフレが起きたことを認め、物価上昇圧力が低下したことを歓迎したが、まだやるべきことがあると述べた。この発言は、市場で最も注目されたように思われる。
この会合に先立ち、ほとんどのFOMCメンバーは、過去40年間で最も高いインフレ率に対抗するため、金利は上昇し続ける必要があり、しばらくはその水準にとどまらなければならないと指摘していた。



テイラールールの考案者であるスタンフォード大学のジョン・テイラー教授はブルームバーグテレビに出演し、インフレへの対応を進めるうえでフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を5%以上にする必要があるとの考えを示した。市場は、4.9%近くを最高水準とした金利見通しを織り込んでいる。
市場は、インフレ、金融引き締め政策、それに伴う米国経済への影響という3要素によって引き起こされる結果については今のところ、あまり考えていないように思われる。
カナダドルにはあまり影響がないが、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルは米ドル安の恩恵を最も享受している通貨である。1日のニューヨーク外国為替市場で、主要通貨に対する米ドルの強さを示す米ドル指数*は、9カ月ぶり安値まで落ち込んだ。
今後の動きとしては、欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行(BOE、中央銀行)がきょう金融政策決定会合を開く。両行はそれぞれ50 bpの利上げを実施すると予想されている。
*米ドル指数は、ユーロ(EUR 、57.6%)、円( JPY 、13.6%)、英ポンド(GBP、11.9%)、カナダドル(CAD 、9.1%)、スウェーデンクローナ(SEK、4.2%)、スイスフラン(CHF、3.6%)に対する米ドルの価値を加重平均して算出した指数である。
60年足チャート - 米GDPとインフレ率
資料:TradingView
--- DailyFX.com ストラテジスト ダニエル・マッカーシー著
マッカーシー氏に連絡するには、Twitter で @DanMcCathyFX までお願いいたします。





